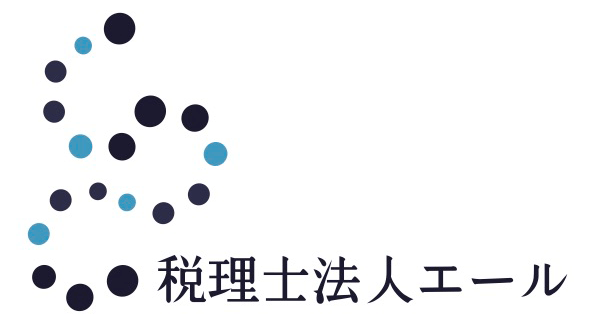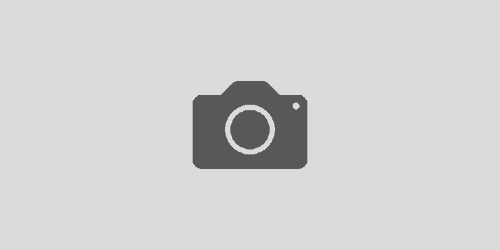相続税の税務調査にむけて準備するべき書類と資料一覧
相続税の税務調査が行われることが確定してしまったけれど、何を準備すべき?
税務署の調査官への対応について、具体的にどんな注意点があるの?
調査官が自宅に来るというだけで、大きな不安をもつ方がほとんどです。
この記事では「相続税の税務調査」に向けて準備するべき資料の一覧表や、対応方法などを解説しています。
税務調査で実際にどのような質問が行われるのか、具体的にイメージできるようにしました。
相続税の専門家として、税務調査に数多く関わってきた税理士経験をもとに、できるだけ分かりやすく書いています。
記事を読んでも分からないことや、
「自分の場合だったらどうなの?」
「資料がそろってないから不安!直接教えてほしい」
などのご質問・ご要望がありましたら、初回無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
安心して相続税の税務調査を受けるために何を準備するべきか
相続税の税務調査の際に何を準備するべきか、具体的な内容と注意点を併せてまとめました。
しっかりと準備するためには、どこまで調べるのか、範囲はどの程度なのかが気になるところでしょう。
じつは相続税の税務調査の場合、相続の対象者に関するお金の流れ等の情報について、すでに詳しく調査されていること多いと知っておいてください。
税務署で把握している納税情報から通帳の中身、不動産の所有や株取引状況まで、あらゆる内容が調べ尽くされた後に、実際に税務調査として調査官が派遣されてくるのです。
わざわざ訪問調査を行うのはなぜかというと、ざっと調べた結果、浮かび上がってきた不明な点を無くすために相続を受ける対象となる人から話を聞く必要があったからです。
そのため、相続税に関わる資料がひと通りそろっていれば、税務調査の時の対応は楽になります。
反対に、必要な資料がそろっていなかったというだけで、証拠が不十分とされ、追加で支払わなければならない税金額が多くなってしまう可能性があります。
実際に、準備不足で税務調査を受けた結果、追加で税金1000万円の支払い請求がきてしまったケースも。
もし必要な資料が集まっていて、税務署を相手にじっくりと交渉ができたなら、1000万円から500万円へと税額が引き下げられる見込みだってあるのです。
たったの書類1枚、ほんの紙きれ1枚で税額が大きく変わるのが、税務調査の実態だといえます。
一般論だけでは分からない部分も多いでしょうから、心配な場合は無料相談をしてください。
通帳から貸金庫の中身まで!税務調査に必要な資料一覧表
相続税の税務調査に使われる可能性の高い資料を一覧表としてまとめました。
税務署の調査官が必ずすべての資料を確認するわけではありませんが、用意しておけばスムーズに調査が進みます。
相続税の税務調査で準備したい資料一覧
- 相続税の申告書を作成時に使った資料(メモや記録も)
- 故人の銀行口座の通帳
- 相続人の預金通帳
- 生命保険の証書
- 生前贈与に関わる契約書
- 贈与税を支払ったことを示す証明書
- 株の取引報告書
- 不動産の権利証
- 葬儀の費用明細
- 香典帳
- 印鑑
- 貸金庫の鍵
一般的に必要な書類の一覧を載せましたが、当てはまる資料のみ準備していただければと思います。
もし適切な資料が準備されていない場合どうなるのかというと、調査官から何か隠さなければならない事実があるのかと勘繰られてしまう可能性が高まります。
書類など形として残っているものがあればいいのですが、何もない場合は事実の確認ができず双方の意見の食い違いがでてしまいがちに。
その結果、調査官と相続人が言い合いになってしまう、または知識不足である相続人側が不利になることが多々起こってくるのです。
相続税を申告した後にも残しておくと安心な資料とは?
身内が亡くなり、相続税を申告する際に使った資料はそのまま5年ほど残しておくといいでしょう。
証書等の正式な書類だけではなく、簡単なメモなども保管しておく価値があります。
相続税の税務調査において一番対応に困るのが、通帳から大きなお金が引き出されていて、何に使ったのかが分からない使途不明金の存在です。
だいたい1ヵ月の間に50万円を超える出金があると、税務署は気になるようです。
使途不明金があったとしても、捜査官に対してある程度説明ができれば、その場をうまく切り抜けられます。
相続税の税務調査を数多く体験してきた中で、意外と多かったのが故人の預金通帳にメモ書きがあるケースです。
帳簿として使っていた場合など、通帳への書き込みは過去の財産状況のヒントになります。
通帳は再発行ができますが、故人のメモ書きは再現できませんので、原本を捨てずに残しておくことをおすすめします。
相続税の申告当時に引っかかりがある場合や申告していない財産があるときは
税務調査について資料がひと通りそろっており、何も心配がないのならば、あまり問題は起こらないでしょう。
ただし相続税を申告していた当時の税理士には言えなかったことや、無申告の財産があってこのまま税務調査に入られてしまうと困る場合は、ぜひ専門の税理士へ相談してください。
これまで、財産を隠していたケースにも対応した実績があるのでご安心ください。
税務署から我が家へ調査官が!具体的な日程とよく聞かれる質問
相続税の税務調査が実際にどのように行われるのか、具体的にチェックしておきましょう。
たいてい、税務署から2名の調査官が来て、約1日がかりで行われます。
【午前】調査官のヒアリング
一般的には午前10時ごろ、税務署から調査官が来ます。
午前中はおもに調査官からの質問に答えることが中心となります。
はじめは雑談からはいり、徐々に核心へとせまる質問へと進んでいきます。
じつは質問の内容に関しては、税務署のマニュアル通りに行われることがほとんどです。
故人に関する話題を中心に、以下のような内容が質問されます。
- 生い立ちや趣味
- 生活の様子
- 日記を書いていたかどうか
- 財産をどのように築いたか
- 投資状況
- 税理士との関係性について
- 亡くなった当時の状況(入院の有無など)
- 相続発生前後の入出金についての確認
- 貸金庫の有無
- 印鑑の確認(使用状況なども)
相続人についてもヒアリングされます。
- 職業や住まいについて
- 家族の年齢や学校名など
- 相続税を納税した金融機関について
- 故人の配偶者の財産状況
- 贈与関連について
かなりプライベートな部分にも立ち入った話になることが多いです。
上記のような、いくつもの質問を通して税務調査官が確認したいのは以下の2つです。
- 申告漏れがないかどうか
- 相続人が財産を隠している、もしくは仮装しているかどうか
形式的には家族の名前で預金しているが、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる預金口座(名義預金)が真っ先に疑われるケースが多いです。
そして、相続税を免れるために生きている間に財産をわたす「生前贈与」が適切に行われていたか、贈与税の申告漏れがないかなど、贈与に関わる部分も詳しく調べられます。
このように、特に調査官が注目しているポイントは
- 名義預金
- 生前贈与
の2つになります。
午前中のヒアリングは、調査官が事前に調べてきた情報をもとに質問をくり返し、事実を確認していくことが中心です。
税務調査官に対して昼の食事は用意すべき?
結論から言うと、税務調査官の分の昼食は用意しなくても大丈夫です。
税務調査が午前10時からスタートして話をしているうちに、あっという間に昼の時間がやってきます。
訪問中の調査官に対して昼食を用意するべきか迷うところではありますが、税務調査官は必ず外で食事を済ませてくる旨を伝えてくるでしょう。
だいたい午後1時に調査が再開されることが一般的です。
この昼休憩の間、2名の調査官は午前中にやり取りした会話を分析し、午後に向けての打合せを行っています。
【午後】現物調査
午後1時からは質問だけではなく、調査官が現物をチェックする作業が行われます。
例えば、以下のような確認がなされます。
- 金庫の置かれている位置
- 通帳など貴重品の保管場所
- 貸金庫の中身
- タンス預金の有無
「ここまで調べるのか」と驚く人も多いのがこの現物調査です。
もし寝室に金庫が置いてある場合、調査官がそこまで同行してしっかりとチェックを行います。
現物調査を終えたあたりから、調査官側から具体的な指摘事項が告げられます。
未申告の現金や預金などの申告漏れがあれば、修正申告を行い、ペナルティとして追加納税をすることに。
相続人が財産を隠ぺいしている、もしくは仮装していると判断されれば、重加算税という重いペナルティが課せられることにつながります。
調査官は家の中にあるもので様々な判断をしている!?
相続税の税務調査に訪れる調査官たちは、相続人の自宅へ訪れた際、用意した質問をする他に、家中に置かれているものをしっかり観察しています。
「ちょっとトイレをお借りします」などと言って、家の中を観察しながら歩き回ることもあります。
何を見ているのかというと、日ごろからどのような金融機関とのつながりがあるのかを探っているのです。
例えば、どの銀行のカレンダーがかけてあるか、金融機関で配っているタオル等の景品などが置いてないか、などです。
所持している車や家具家電、インテリアの傾向などからも、様々なことを読み取られてしまいます。
これに対して相続人側は何もすることはないのですが、下手に隠そうとするそぶりを見せると調査官から不審がられてしまうだけなので、オープンな姿勢で対応する方がいいでしょう。
相続税の税務調査を受けた後に再調査はある?
相続税の税務調査が1度行われたら、ほとんどの場合、再調査を受けることはありません。
もし新たな財産が見つかったのならば、あらかじめ修正申告をしておけば再調査に至ることはないでしょう。
心配なのであれば、今回の税務調査で使った資料をもうしばらく保管しておくといいですね。
相続税の税務調査における税理士の役割
すでに相続税の申告をした際に、税理士に依頼した方も多いことでしょう。
税務調査においても、税理士に頼むのが一般的な流れです。
ただし、税理士にも得意な分野とそうでない分野があります。
あなたの担当の税理士は、相続税の税務調査についてどれくらいの実績があるのかをご存じでしょうか。
例えば、税務調査の際に同席してもらって安心なのはどちらだと思いますか?
- 税務調査が実施されると分かり、バタバタと焦って準備を行っていた税理士
- 数多くの実績があり、税務調査でどう対応すべきなのか熟知している税理士
おそらく後者が隣に座っている方が、心強く感じることでしょう。
税務調査に慣れている税理士かどうかは、対応の差だけではありません。
もし修正申告を行うことになった場合、税理士の違いによって追加で支払う納税金額についても大きな差が現れます。
実際に税理士に依頼した場合の実例
相続税の税務調査が入り、名義預金が指摘されてしまったケースについてです。
依頼する前
重加算税というペナルティをうけて、1000万円の税金請求が来てしまいました。
税務調査に詳しい税理士に依頼した結果
論点の整理や交渉を行い、500万円の税金のみで決着したのです。
その際の税理士報酬は、100万円でした。
何もしなければ、そのまま1000万円が手元から消えていくだけ。
税務調査に詳しい税理士に頼むだけで、依頼者が出すのは600万円のみに抑えられ、400万円も手元に多くのお金が残るのです。
ちょっとした差が大きな金額の差につながるのです。
もちろん、すべての税務調査において、税金を抑えられるわけではありません。
家庭ごとにそれぞれ事情がありますので、まずはお話をお聞かせください。
まずは電話・メールで専門の税理士に相談を
税理士法人エールでは、電話とメールどちらでもご相談を受け付けております。
抱えている思いを一気に話してしまいたい方や、文章として残しておきたくない話がある方は電話を。
いきなり電話をするのが苦手な方や、考えを文章にまとめながら相談したい方はメールでの相談をお選びください。
相続税の税務調査は、様々な情報が絡み合う、とても複雑な案件です。
その道に詳しい税理士に相談していただければ、悩みを少しでも軽くすることにつながるでしょう。
元国税局の調査官が対応!ポイントを押さえたアドバイスが聞けます
じつは税理士法人エールには、国税局の調査官として働いていた者が在籍しております。
相続税の税務調査がどのように行われるのか、熟知しているということです。
これまで調査官としても、税務調査を受ける対象者としても体験してきた実績がありますので、スムーズな対応を実現いたします。
ここまで読んできた中で、相続税の税務調査について、自分たちに何が当てはまるのかどうかなど、数多くの疑問点が頭に浮かんでいることでしょう。
電話でも、メールでもかまいません。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
(正式にご依頼いただくまでは1円も発生いたしません)